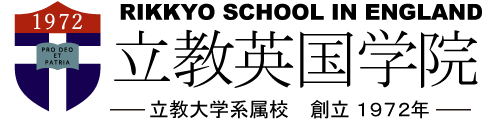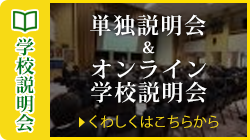立教のHPを拝見させていただきました。相変わらずの恵まれた環境で学生さん達が生活できるのは、うらやましいです。僕が中2のときに入学した時はまだプレハブ時代でしたから、建物など随分と立派になったと感じました。
また、写真でお世話になった多くの先生方がまだいらっしゃるのを見て、思わず嬉しくなりました。当時反抗ばかりしていた自分が恥ずかしいですけど、まだ皆さんがいらっしゃる間に立教にお邪魔したいものです。
Science Workshopは素晴らしい企画ですね。うらやましい!自分も30代半ばとなり随分と頭が固くなってきたことを嘆いていますけど、柔軟な10代からそのような経験ができることは、本当に恵まれていますね。
人間は自分のもった夢の大きさ以上の人間にはなれないと思っていますので、生徒の皆さんには大きく夢を持ってほしいものです。
被災地で思ったことのレポートと写真を添付しました。今後も、僕にできることがあれば何なりとおっしゃってください。
* * * * *
【未来への切符-被災地での2週間】
18期生 渡瀬剛人
2011年3月11日。テレビの津波映像から目を離せなかった。オレゴンにいた自分は、その現実を実感できないでいた。しかし何回もその映像を見せられるうちに、それが現実であることを無理矢理押し付けられた。すぐに被災地に飛び立ちたいという衝動と仕事と家族に対する責任の狭間で、心は揺れ動いていた。二週間後、自分は被災地、本吉(気仙沼市近郊)にいた。
被災地に向かう車の中からみる景観には驚かされた。大地震が起こったはずなのに、何事もなかったかのように建物は整然と立っており、道路は滑らかで、畑には農作物が植わっている。しかし、ある点を過ぎたら全てが変わった。建物はおろか秩序そのものがなくなっている。変わりに、ゴミの山と混沌が辺りを支配していた。
着いたのは本吉市にある市民病院。30床ほどの小さな2階建ての病院。倒壊は免れたが、津波時には1階は水没。1階にあったCT、検査機器、カルテ、エレベーターなど全てが使い物にならない。電気のスイッチを入れても、スイッチの音だけが悲しく響く。水道の蛇口をひねっても、出てくるのは水数滴のみ。寝食と診察をする2階に荷物をおろし、自給自足の生活が始まるのだと自分に言い聞かせ、寝心地の悪い床で眠をとる。
患者さんは、避難所や自宅などから来院する。一日に200人以上の患者さんが様々な訴えをかかえて来院する。単なる風邪や関節痛から、命に関わる呼吸器疾患、心臓発作、脳梗塞と色々だ。 まず大変だったのは、エレベーターが壊れて使えないので、自力で2階に上がれない患者さんは、担ぎ上げないといけない。また、まともな検査もできないため、医療の原点である問診と診察が大切となる。薬も例に漏れず不足しているために、数日分しか処方できない。こういった状況では最高の医療を求めていてはダメだ。最善の医療を求めようと心に決めた。
東北の人たちは気丈だ。患者さんの中には家を流された人、家族を亡くした人が多くいる。しかし、皆、決して取り乱すこともなく、礼儀正しい。また、それぞれの訴えが氷山の一角であることも知る。ある中年女性が「肩が痛い」という訴えで来院した。肩の痛みに対して痛み止めを処方して帰そうとし、何気なくどうしたのかと聞いたところ、聞き入らずにいられなかった。その女性は津波に流され必死で家の屋根にしがみついていたところ、流れてきたタンスがぶつかってきて肩を痛めたとのこと。その衝撃でまた更に津波にのまれ、どうして自分が助かったのか分からないと小声で言っていた。被災地では、単なる「肩の痛み」が、とてつもない重さをもつのだ。
被災地での活動が終盤に差し掛かってきた頃に、ふと疑問がわいてきた。自分は多くの患者さんを診てきたが、果たしてどれほど役に立ったのか分
からなかったのだ。自己満足に浸っているだけかもしれないという不安がよぎった。そんな時に出会った、ある患者さんのことが忘れられない。この患者さんは初老の女性であり、コレステロールの薬を処方してもらうために来院していた。
女性:(薬を胸に抱きしめ)先生、本当にありがとうございます。これで助かりました。ホッとしました。
自分:薬ぐらいでそんなに感謝しないでください。こっちが恐縮するじゃないですか。
女性:(しばらくの沈黙の後に)私は、赤子の孫以外の家族全員を津波に奪われました。孫にとって唯一の肉親が私です。孫が成人するまでは私は頑張らなきゃならんのです。病気にはなれんのです。この薬は他の人にとっては単なる薬かもしれんけど、私にとってはかけがえのないものなのです。この薬は私にとって未来への切符みたいなものです(そう言って彼女は大切そうにその薬をしまい、お辞儀をしながら部屋を出ていった)。
被災地で医者として何ができたか?正直、大きなことは何もできなかった。 しかし、薬を処方すること、手を握ること、話を聞くことは何十回、何百回としてきた。そういった行為が、患者さんにとって未来への切符ともなればいいかと、少しだけ安堵の表情を浮かべながら自分は被災地をあとにした。
* * * * *