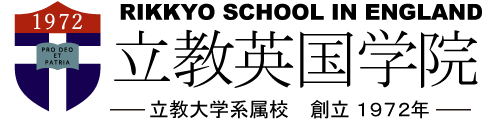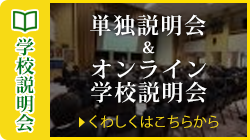遠藤周作の『沈黙』がスコセッシ監督によって映画化され、日本でも、イギリスでも公開され話題となっています。江戸時代のキリシタン弾圧という限界状況を通して、遠藤周作自身の信仰を描くという小説です。
この『沈黙』の舞台である長崎とその西百キロに浮かぶ五島列島へと、以前私が牧師をしていた教会の信徒の方たちと巡礼に行ったことがあります。
戦国時代や江戸時代だけではなく、幕末から明治にかけても、キリスト教迫害の歴史が日本にはあります。明治の始めに、長崎の浦上のクリスチャン、約三千四百人は全国約二十箇所に連れて行かれ、六百十三名が殉教しました。たった百五十年ほど前のことです。
長崎から西へ約百キロ離れた五島列島からは、そう簡単に全国各地に連れて行くことができません。そこで、同じ島内で、同じ島民によって迫害が始まったのです。
ひどい牢ですと、たった六坪に二百人が押し込まれて衰弱死をしました。拷問で殺された人も数多くいました。
クリスチャンだから殺してもいいという理由で、刀の試し斬りのため、夜中に家に押し入られ、妊娠している女性も含めて六名が切り捨てられたということもあります。
明治の二十年頃、ある司祭が臨終の信徒を看取るため、嵐の中十一人の若い信徒達と共に小舟で長崎本土から戻る途中に遭難してしまいます。助けに来た島の男達が船に乗り込むのですが、船には新しい聖堂を建てる資金がありました。そのお金のために、司祭含む十二人のクリスチャンは殺されたのです。
これが何故わかったかというと、助けに来た男達の中に一人のクリスチャンがいたのです。彼は周りが怖くて止めることができず、司祭たちを見捨てたのでした。それは彼が臨終の時に、いてもたってもいられず告白したことによってわかった事実です。
これらのエピソードはガイドブックや文献の中には余り描かれていません。というのは、これが同じ島の中でたった百五十年ほど前に起こった出来事だからです。
加害者と被害者と傍観者に、逃げ場がないのです。ずっと顔を合わさなければいけない、それが島の環境なのです。
そこにはどれほどの葛藤があることでしょうか。加害者側は、罪意識を持つかもしれません。あるいは、かえって差別意識を持つかもしれません。被害者側も、彼らを赦せないままかもしれません。何十年経った後でも、殺した子孫と殺された子孫が同じ島の中に、逃げ場のない島の中で生活しているのです。
長崎のクリスチャンたちは、様々な時代において何を待ち望みながら、祈っていたのでしょうか。
それは自由です。一つは信仰の自由があるでしょう。もう迫害されない、いじめられないという安心、平和という自由でもあります。それをもっと深めますと、罪からの自由、赦しということに他なりません。
やってしまったという罪意識からの自由だけではありません。罪を赦すことができない、どうしても憎い、このことからの自由、自分の人生に絡みついた様々なことからほどかれるということ、これが罪からの自由、赦しなのです。
復活日(イースター)の物語では、十字架に架けられて三日目に復活されたイエスが、家に隠れて集っていた弟子たちの真ん中に現れた、という箇所が読まれます。弟子たちは互いに罪の意識を持っていました。彼らは自分も殺されるのではないか、という恐れのためイエスを見捨て逃げ出していたのです。彼らは被害者でもあり加害者であり傍観者でもあったのです。
そこに主イエスが現れ、手を広げられます。その手には十字架の傷、弟子たちがつけてしまった傷が刻まれたままです。イエスは傷ついたままの手を広げられて、彼らに「平和があるように」と告げられ、パンとぶどう酒、聖餐(せいさん)(ミサ)の準備をされるのです。
傷ついた手を見た時、その手が自分に差し伸べられた時、その手からパンとぶどう酒が、自分たちの「人を傷つけた手」、「人に傷つけられた手」に渡された時、どれだけの自由を、赦しを、愛を、彼らは受けたことでしょうか。
人は愛されたから、誰かを愛そうとすることができます。赦されたから、誰かを赦そうとすることができます。この喜びを伝えるために、教会は作られ、世界中に広がり、毎週日曜日に聖餐式が続けられているのです。
ですから、長崎の人々にとって、キリスト教禁制の250年の時を経て、聖餐式にあずかることがどれほどの喜びだったことでしょうか。明治になっても自分の親や子供が殺された中で、日々の中で、聖餐式にあずかることがどれほどの慰めとなったことでしょうか。
そして誰よりも、神ご自身が、人々が慰め合い、愛し合い、自由に生きることを、強く待ち望まれているのです。
私たちがこのことを深く思いながら、日々を送ることができるよう、お祈りしております