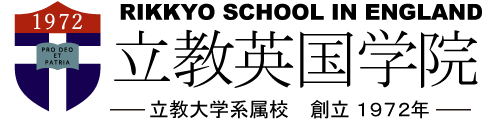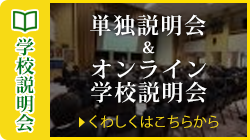「檸檬」という題名を見て、まず僕の頭に浮かんできたのは、あの「黄色い果物」という以外には何もなかった。どのような話が描かれているのか、想像するのさえ難しかった。最初の数行を読んでみただけで、あまり自分好みではないと感じた。なぜなら、僕と作者との世界観が全く違うし、普段僕が読んでいる小説のような爽快さやおもしろさがこの作品には全くと言ってよいほどないからだ。
主人公の私は病気が進行するのに従って、物の見方が変わってきていると僕は思う。昔、大好きだった場所や物がだんだん憂鬱になっていき、重苦しい場所に変わってくる。僕にも似たようなことはあった。ドイツに来たばかりの頃は大好きだったスーパーマーケットが今では面倒な場所になってきた。だけど僕の場合は、年齢に伴って親について買い物に行くよりは、その時間を自分のために自由に使いたくなったからであって、作者のように病によって生活が蝕まれて物の見方が変わってしまったわけではない。作者の大好きだったものが重苦しいものになる悲しみや苦しみは、健康な僕には到底理解することができない。
この作品を読み進んで、僕が一番印象に残っているのは、作者が久しぶりに入った丸善で、バラバラとめくった本を積み重ね、その上に檸檬を置いて店から出て行ってしまう場面だ。僕がその中でも特に印象に残っている一節は「私にまた先程の軽やかな昂奮が帰って来た。私は手当たり次第に積みあげ、また慌しく潰し、また慌しく築きあげた。」だ。僕も似たようなことを衝動的にしたいと思ったことがある。例えばスーパーマーケットで、お菓子の箱を全て棚から出して大きな家を作ってみたらどうだろう。本屋のマンガコーナーで一巻から最終巻までの並び順を全く逆にしたら、次にそのコーナーに立ち寄った人はどう感じるだろうか。想像するたびに体中がゾクゾクしてきた記憶である。ついつい手が伸びそうになるのを僕の理性が必死になってくいとめている。「近くに自分の知り合いがいたらどうしよう。」「店の人に怒られるのではないだろうか。」僕の中の臆病な部分がこのようないたずらをしたいという気持ちに勝るのだ。だから僕は疑問に思う。なぜ、作者は思ったことを実際に行動に移せたのだろうか。また、この時には周りに店員又はお客がいなかったのだろうか。もし、僕がこの作者のような行動をしている人を見かけたら、迷わず注意するか、店員に知らせていただろう。だから僕は不思議でならない。なぜ誰も主人公をとがめなかったのだろう。気がついた人はいなかったのだろうか。もしかしたら、主人公には自分以外の世界が全く見えていなかったのかもしれない。ここに続きは描かれていないが、この後、主人公は丸善のこの現場に戻って来たのではないかと思う。僕なら間違いなくそうしたと思う。
主人公が、檸檬を手にとったことにより、今までの不吉な塊が少しずつやわらいでいき、幸福な気持ちになったように「檸檬」には不思議な力があるのではないかと思う。高村光太郎の詩集「智恵子抄」の中の一つ「レモン哀歌」の中に
「その数滴の天のものなるレモンの汁は
ぱつとあなたの意識を正常にした
あなたの青く澄んだ眼がかすかに笑ふ
わたしの手を握るあなたの力の健康さよ」
とある。智恵子が檸檬を噛んだときに、彼女が一瞬でも意識を取り戻し、元の元気だった頃の智恵子に戻ったと思う。檸檬のさわやかさ、水々しさ、そのすっぱさが「不吉なもの、もやもやしたものを吹き飛ばしてくれる。」「その人に生気を取り戻させてくれる。」そんな力があるのかもしれない。梶井基次郎も檸檬の不思議な力を感じ、勇気がでて、また、幸福な気持ちになることができたのだと思う。
正直僕はこの感想文を書くのにとても苦労している。とても美味しそうに檸檬を食べている妹と母を見ていると、うとましくさえ思う。さわやかなはずなのにと黄色い物体に文句を言いたくなるが、言っても何か答えてくれるわけでもないので何か言うことはない。しかし、あと少しで書き終えたら、僕はとてもさわやかな気持ちで檸檬を食べたいと思う。
(高等部1年生 男子)