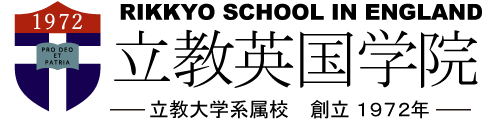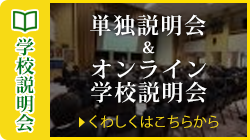中学校3年生の国語で「朝焼けの中で」という単元がある。作者は八つか九つくらいの年の頃、朝焼けを言葉で表現しようとするものの、その美しさに圧倒され、言葉で表現することの限界を感じた、という話だ。
作者は言う。「私はあの朝、初めて言葉というものの貧しさを知ったのである。」「自然の表現の見事さに、人のそれは及びようのないことを、魂にしみとおらせた。」と。
「みんなは、こういう言葉の表現できることの限界を味わったことはある?」という問いに、「分かるような、分からなくないような……」という返答。ということで、自然の美しさを言葉で表現することに挑戦してみようということになった。その頃丁度立教は、満開の桜。桜の花の美しさについて、それぞれ表現するために、みんなで桜を見に行った。桜の色のグラデーションの具合や、枝や花びらのつき方、花びらの動き、光の当たり方、空気感などに注目して、スケッチしていくかのように書くことや、比喩表現を使用すると効果的であることを指導した。以下、生徒の作文である。
* * * * *
冷たい風の中で、粉雪のように白い花びらを散らせる桜の木。春のおとずれを感じさせるその姿は、自然の冷酷さに抗いながら、たくましく生きることへの喜びを表しているようだった。
(中学部3年 男子)
淡い桃色の花びらが幾重にも重なり、風景に透けこんだ。独特な甘い蜜の香りに誘われて、蜂が盛んに行き交っている。それまでかくれんぼしていた太陽が眩しい程の光の粒を地面にふりそそぐ。一瞬生み出された影が、儚げな存在を濃く主張していた。風も形の無い存在感を、枝を通して伝える。ゆれる枝は風の向きに合わせて小さくざわめいた。散りゆく花たちの優雅な舞踏と光の粒子が交じり合って白銀の光線を放つ。遠くから見ると、淡い桃色で縁取った緩やかな曲線が一際目立つ。母の様に優しく、しかし怖いくらい美しく力強い生命の神秘はしっかりと大地に根をはりめぐらせている。やわらかな花を芽吹き、丈夫な枝を持つこの生命の一本は、何年もかけて培ってきた命の証なのだ。この季節しか咲かないこの花は、人々を魅了すべく、今日も満開の花で曇天を彩っている。
(中学部3年 女子)
ちょっと蹴ったら、ぽっきり折れてしまいそうな枝から、純真無垢な白い花が力強く生きている。花の深い部分は、紅に染まり、それが集まって一つの淡いピンク色の木となる。枝の先からは、緑色の芽が噴き出て、新しい命の始まりを告げている。風が吹けば舞い踊る花びら。まるで盛者必衰の儚さをうたっているようだ。既に命の終わった花びらは、色も変わり、本来の花の華やかは失ったが、そこからは、やがて土になって、またさらに木の栄養となっていく、そんな命の連鎖を感じさせる。
まっさおという程青くなく、水色という程薄っぺらくない。層のように積み重なった、しかしそれでいて透明感のある空に、まるで重力など存在しないかのように、漂白されたシャツぐらい白い雲。そこから降り注ぐ太陽のあたたかく優しい光の粒に照らされて、桜は今日も生きている。
(中学部3年 女子)