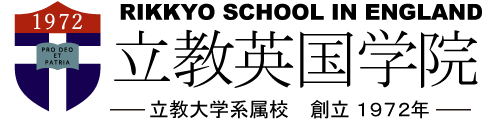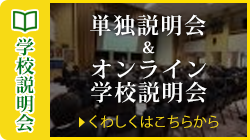森鷗外の作品を読むのはこれで三度目だった。有名かつ偉大な作家なだけに、彼の作品の中でも高く評価を受ける、「高瀬舟」は授業でも取り扱った。他には「青年」を読んだが、今作品はそれら二作とは大きく異なる印象を受けた。雁には高瀬舟にみられる思想的葛藤も、青年で登場するような哲学者や知識人もいない。しかし最後だけは森鷗外らしい希望を全て打ち砕かれたような遣る瀬無い終わり方をしている。
話の舞台は明治十三年、主人公の「僕」によって話は語られる。そして中心となるのは僕と同じ大学に通う岡田と、二人の散歩道に住む高利貸しの妾、お玉だ。お玉は妾という立場で自由は拘束されているが、家を通りかかる岡田に惹かれていく。しかしその思いは届かぬまま物語は終わる。岡田はドイツへ留学することになり、それを知らないお玉は何気なくすれ違うのを最後に儚き別れを遂げる。
この本において森鷗外が最も描きたかったのは、一女性の自我の目覚めとその挫折であろう。つまり若き男女の恋愛などには端から興味がない。岡田の心境など描写が成されていないのが何よりの証拠だろう。しかしそう考えるならば、「雁」というタイトルに違和感が生まれる。雁が実際に登場するのはまさに物語の終盤、岡田が投げた石が偶然にも雁に当たり命を落としてしまう。そしてその雁を持って帰って食べることになり、そのせいでお玉は岡田に会えず終いとなった。
確かに物語を動かしてはいるがこの一羽の雁が話の中心にいたとは考えられない。ならばなぜ作者は雁を、本の顔とも言える、タイトルに選んだのか。それは、雁の一生がいわばこの本の象徴であるからだと考えた。
雁は渡り鳥である。渡り鳥は秋に、冬の寒さから避けるため日本や周辺の温暖な地帯へ海を渡って移動する。そして気温が暖かくなるとまた北の寒冷な地域へ飛んでいく。本文中に明確な季節の描写は無いが、雁が登場したのが岡田の留学前夜だということから、春だと考えられる。つまり命を落とした時雁は新しい住処へ飛び立とうとしていたのだ。
そう考えるとお玉と雁の人生はどこか似ているように思えるのだ。お玉もまた新しい、岡田という、心の居場所を求めて飛び立とうとしていたのだ。そして結果、雁もお玉も突然の終わりを迎えるのだった。石が当たり落下する雁のうな垂れた首は正にお玉を象徴していた。この辺りが、森鷗外が雁をタイトルとした理由であろう。
お玉と岡田の別れにより物語は終わる。これだけを見ると救いようの無い話のように思えるが、そうとも感じられないのだ。確かにお玉の想いは届かず、雁のように彼女の恋心は殺された。しかしあくまで恋心というのはその時の気持ちであり、お玉自体が死んだわけではない。つまりそこに、冒頭で言った、「他の作品と大きく異なる印象」があるのだ。
例えば、高瀬舟は読み終えたあと、どうあがいても這い上がれない闇に落とされたような感覚を受けたが、雁はあくまで一つの恋の話、またはその恋により自我が芽生える、要は成長する女性の話だ。いくら妾という立場でもそこに死が待っている訳ではない。お玉はこの物語が終わっても生きていくし、また新しい恋をすることもできるのだ。
そして作者も最後に読者に想像を煽らせる一文を残している。
「お玉とはその後相識となったが、それはなぜかと問われても、これに対する答は物語の範囲外にあるため読者は無用の憶測をせぬが好い」
こんなことを書いておいて想像をするな、という方が無理がある。どういった経緯でこれが書かれていようとも、お玉はそれなりに岡田が居なくなった後も、正常に生活を送れているということだ。
雁は森鷗外の作品の中では読みやすいという印象だったが、淡々とした、しかし切ない文章は余韻を残した。そして読み終えた後、考えをめぐらすのも彼の作品特有だ。本の中の解説部分にも、作中での出来事や解説はあるが、心の中のもやもやは消えない。作者自身の狙いがこのもやもやなのならば、彼の手の上で踊らされる読者の一人なのだが、それすらも知ることはできない。こうして彼に興味を持った自分は他の作品も読むことになるだろう。しかしそれもまた森鷗外の狙いなのかもしれない。
(高等部1年生 男子)