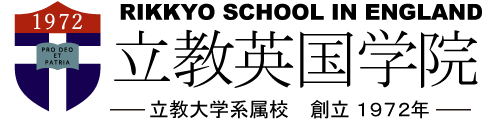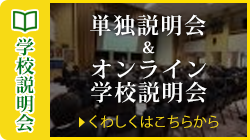両手にタレの付いた軍手。背中には青地に「祭」と書かれた赤の文字。耳からは僕が好きなRADWIMPSの曲が聴こえる。目の前には銀の金網にのった串刺しの肉とネギ。さらに顔を上げると、こっちを見てくる人、横を見れば自分と同じような青い職人。
思った以上に忙しかった。職人を離れられたのはラッフル(福引)に行った時と、先生にドラヤキをおごってもらいに行った時くらい。ラッフルは5年間やってもB賞すら取れない。人におごってもらったからか、ここで食べるのが最後だからか知らないが、そのドラヤキは妙に美味しかった。食券のパンや和菓子や飲物は全部人に頼んで買ってきてもらった。これもまた頼んだ女の子が可愛かったからか、ここで食べるのが最後だからか知らないが、どれも妙に美味しく感じた。大好きな「彩しらべ」を大嫌いな「抹茶せんべい」と間違えられたのはさすがに頭にきたが…
思った以上に、いや予想通りだったかもしれないが、楽しかった。焼くと、「今年は美味しい」、「ベリーナイス」、「ネギ美味しい」などの声が聞こえる。素直に嬉しかった。また、そんな風に思われる職人になったことも楽しかった。でも、この職人になれることが今回で最初で最後と思うと悲しい気持ちもした。
「職人」。良い響きだ。僕らには肉を焼く職人、ハケでタレを塗る職人、肉をお客さんに配る職人がいた。どれも良い職人。まさに縁の下の力持ちという職人だ。お客さんの為に、千本売り切るためにという皆の思いは、大きな団結力を生んだ。それは僕が久しく目にしていないものだったからか、眩しいものだった。
結局、僕たち職人はヤキトリを全部売り切った。しばらくして、経緯は忘れたが僕は手に唐揚げ棒を持って、白いテントの下の椅子に座っていた。さっきまで賑やかだった中庭も人が減った。もうこんな団結力を感じたり、オープンデイを経験したり、この賑やかだった中庭に人がいなくなって空虚な思いをしたりすることはない。何よりこんな風にヤキトリを焼くことはないし、この学年で何かをすることはない。唐揚げを一口食べた。美味しくなかった。少し冷めていたからか、少し水で濡れていたからか、美味しくなかった。こんなものいくらでも日本で食べられるのになぁ。もうこれからこの職人になることはない、僕はそう思っていた。
(高等部3年生 男子)