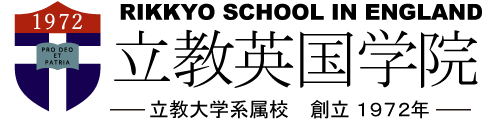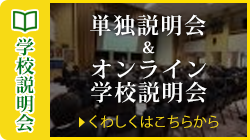未知の世界へと続く扉の前で、期待に目を輝かせる魔法使いの卵たち。この地球上で最も有名な丸眼鏡の少年も、その列の中にいた。
学都Oxfordで英国ならではのHigh teaを存分に楽しんだあと、わたしたちの班の好奇心をくすぐったのは、眺望の良い教会ではなく、アインシュタインの黒板でもなく、Christ Church Collegeだった。5.5poundsの入場料を払って入った先は本の中の学校にそっくりで、どこぞの怪物(トロル)が出没しそうな石の回廊や、箒が風を切って飛んでいってもおかしくない緑の中庭が、目に眩しかった。けれどその中でも一番わたしの心を動かしたのは、荘厳な食堂だった。
重々しい木調の長いテーブルにひっそりと置かれていたメニューには”Freshers”の文字。それを見て思い出すのは、キャンパス内を案内して頂いてるときにすれ違った人々のことだ。自分と大して年の変わらないだろう若い人から、その保護者か、或いは第二の人生を歩み始めるつもりなのか、髪に白いものが多く交じった人まで。皆一様に、喜びと希望に満ちた顔で、寒空の下に立っていた。新入生のためのイベントに、参加するためだ。彼らが今夜、あの魔法使いの卵たちのように、石の階段を登り、大きな扉の向こうへと入ってゆくのだ。そう思うと、不思議な感情が湧いた。
尊敬。今和やかに談笑している彼らがここに辿り着くまでには、一体どれだけの努力があったのだろう。
憧れ。名門Oxfordの学生の一人であるというのは、どのようなものなのだろうか。
感動。ここに居る人々が、やがては様々な学術の権威として、世界中に広がってゆくのだ。
そんな純粋な思いの中に、今の自分自身を見つめている冷静な目があった。日本を飛び出して英国にやってきて、国の垣根を越える新時代の大人になるための視野は広がったと思っていた。けれども目前にある試験、日本の大学への進学のことを考えているうちに、それは再び、少しずつ霞んできた気がする。自分の能力を高めるために海外へ出たとして、今見ているトップクラスの学都へ進学したとしても、その場所でさえ、まだ世界のほんの一部なのだ。秋の高い空に、それを気付かされた。
Christ Church Collegeの食堂へと続く扉は、確かに新しい世界へとつながっているだろう。だが、そこで終わりではない。日本の大学を出てから取り敢えず海外へ出ようと漠然と考えていたわたしには、当たり前のことのはずなのに、少なからず衝撃だった。井の中の蛙は、話には聞いていた大海を見た。さて、わたしはこの後、何枚の扉を開けることが出来るのだろうか?
(高等部2年生 女子)