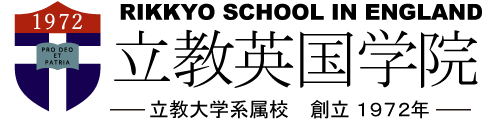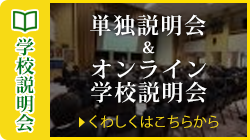毒々しいくらいの真紅に染まり、剥き出しになった「ソレ」を前に、私は心を奪われていた。
「ドン。」
大きな爆発音。ようやく我に返り視線を上げる。そこには絶えることなくつぎつぎと夜空に咲き乱れる満開の花々。咲いては散り行きそして一瞬にして全てを出しきる。微かな火薬の匂いと共に今年も美しく、盛大にまた色鮮やかに咲いていた。
ふと視線を落とすとステンドグラスの様に不透明な艶を帯びたソレは空を舞う色取り取りの花火を反射し、また更に美しく映していた。そして私は表面に前歯を押し当て、ためらうことなく噛み砕いた。口内に広がる真っ赤に染められた水飴の強い甘み。口の中で溶けそして喉を通る。蜘蛛の巣状にひび割れた真っ赤なガラスはとても魅力的だった。さらにガラスの真ん中からのぞく肌には粉々になった赤い染粉が潜んでいた。
しかし最初の一口以降は、つまらないくらい平和な咀嚼が続くだけで私はすぐに興味を失ってしまった。
噛み砕くという少し暴力性のある行為。その行為により一瞬にして壊され、奪われるソレの完全性。美しく盛大に、また真っ赤な物が作られては壊されていく。そんなどこかが夜空に舞う花火の様で。魅力的で。「一瞬。」という物の美しさ、そして儚さを表している様に私には思えた。そして巨大な何輪もの花々もやがて最後には真っ暗な闇の中に消え、私の右手に咲いていた一輪の花も軸だけを残し跡形もなく消えてしまった。
私の記憶の中に残されたこの夏の思い出さえも次のこの季節にはまた違う色に塗り変えられているのだろうか。夜空に残った灰色の大きな煙を見て私は少しさびしく思った。
(中学部3年生 女子)