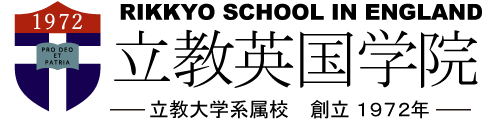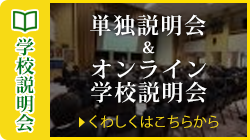合唱コンクール。クラスメイトと試行錯誤しながら、自分達なりの世界を作り上げる。男子と女子が共に奏でるそのハーモニーは、とても美しい。
今回、私のクラスは「青いベンチ」という曲に挑戦することにした。この曲を一言で表すと「悲恋」だ。
「この声がかれるくらいに君に好きと言えばよかった。会いたくてしかたなかった。どこに居ても、何をしてても。」
この歌詞をただ単に歌い上げるのは簡単だ。しかし、聴き手に伝わらなければ、そんなに良い曲を歌っても意味が無いのだ。まだ十六、七年しか人生を歩いてきていない私達に、こんなにも熱い恋心でいて悲しい恋愛ソングに感情移入し、歌えるとは思っていなかった。その場のノリで選曲してしまったものの、後々から不安が募っていたのは、私一人だけではなかっただろう。
しかし「合唱」というものは「歌」だけでは成り立たない。伴奏者と指揮者が必要不可欠だ。
今回も伴奏で皆を支えようと決めていた。もちろん歌を歌うことは大好きだ。しかし、どうしても伴奏がしたかったのだ。学生生活の合唱コンを全て伴奏で終わらせたかった部分もある。でも本当の理由は全く違う。
冬休み、私は知り合いの方の演奏会に行った。その方は、私が「音楽」を嫌いになっていた時期に、もう一度、音楽の楽しさや素晴らしさを教えて下さった方だ。その方の演奏会で感じたものを、今度は私自身が聴いている人に伝えたいと思ったのだ。また、今年は私のピアノ人生十五年目突入の年であり、一つの節目の年でもある。今のピアノの先生に習って十年以上が経った。しかし、将来、ピアノに頼って生きていくことはないだろう。今回が人前で弾ける最後のチャンスだ。今まで支えてくれた方々に感謝と、そして、私の今できる全てを注いで弾きたいと思ったのだ。
学校に帰ってきて指揮者と歌を合わせる。だが、何かがずれていた。強弱だ。たった一小節だが、違えば全体図が変わってしまう。指揮者と話し合って一件落着、といきたいが、そう単純にいかないのが現実で、何度も何度も口論になったのは、今では良い想い出だ。
一週間という短い練習期間を終え、迎えた当日。発表は全校で最後だ。「トリだからこそ、今年の合唱コン自体が良い物で終われるようにしよう。」「総合優勝しよう。」そう意気込み過ぎていたのか、少しばかりテンポが速く、表情も硬くなっている気がした。
しかし毎日、聴き手側だったからか、直感で分かった。「あ、これは優勝だな。」と。良い意味でいつもと違っていたのだ。このクラスの長所である「何時でも声が大きいこと」と「想像力が豊か過ぎること」が全開だったからかもしれない。
伴奏も悔いが無くはないが、それでいて観客を魅了し、場面を想像させる最高の手助けができたのではないかと自負している。私らしい伴奏ができた。
こうして終えた合唱コンクールは、歌声ダイヤモンド賞、校長特別賞、そして総合優勝の三冠を成し遂げた。あの結果発表の時の皆の驚きと、弾けるような笑顔を私は忘れることがないだろう。
このクラスの一員で本当に良かった、と思えた一日となった。
(高等部2年生 女子)